無効な入力です。特殊文字はサポートされていません。
操作方法を覚え直すのが面倒で、スマートフォンの乗り換えをためらったことはありませんか? また、似たようなアプリばかりで、どれが必要なのか分からなくなったことはありませんか? ホテルの予約、航空券の予約、経路の計画、予算の管理など、1回の旅行のためにいくつものアプリを開いていませんか? 最高のインターフェースであれば、このような混乱をすべて解消できるはずです。さらに、そのインターフェースに変化があっても、手間を感じさせず、ほとんど意識することもないはずです。これこそアンビエントAIが約束するメリットです。テクノロジーが背景に溶け込み、暮らしがより快適に感じられるようになります。現在、新しいパターンが生まれつつあります。話したり、ジェスチャーをしたり、単に生活を送ったりするだけで、スマートフォンが次の最適な行動を予測してくれます。例えば、指を鳴らすだけで、週末が記念日だと知っているスマートフォンがディナーの予約をしてくれるといった場面を想像してみましょう。これほどのシームレスな自動化はまだ一般的ではありませんが、この例は、ユーザーのニーズを予測し、先回りして行動するテクノロジーというアンビエントAIの本質を表しています。現在、Google アシスタントやOpenTableなどのツールにより、この方向への動きはすでに始まっています。これらのツールは、ユーザーの好みや過去の行動に基づいて予約を提案・実行することができます。将来的には、このようなやり取りを簡単かつ直感的に行えるようになることが重要です。このような手動操作から見えない支援への移行こそ、AIが新しいUI(インターフェース)となる理由です。
この変化の中心にあるのは、オンデバイスAIです。スマートフォンが知能を備えることで、オフラインでも、自分に合わせたエクスペリエンスを即座に得られるようになります。そうしたエクスペリエンスを支える基盤となるのが、縁の下の力持ちであるメモリです。リアルタイムの会話も、即時翻訳も、先回りの提案も、すべてはデータがシステム中をいかに早く移動できるかにかかっています。AIモデルの巨大化と複雑化が進む中、より多くのメモリがあれば、クラウドへのデータ送信なしに、デバイス上だけでAIモデルを動作させることができます。
しかしアンビエントAIは常時バックグラウンドで静かに動作するため、バッテリー駆動時間への影響が懸念されます。そこで不可欠なのが省電力メモリです。省電力メモリがあれば、応答性を保ちながら、バッテリー駆動時間を伸ばすことができ、その結果、応答性の向上、消費電力の低減、プライバシーの強化が同時に実現します。
なぜ今なのか:環境の変化がアンビエントAIに道を開く
アンビエントAIが主流に
最近のSamsung Galaxy UnpackedイベントとMade by GoogleのPixel 10発表イベントにおいて、SamsungとGoogleはそれぞれ、AIが日常生活にシームレスに溶け込む未来像としてアンビエントAIのビジョンを示しました。モバイルUX(ユーザーエクスペリエンス)の観点から見ると、この進化は、これまでのようにユーザーがインターフェースに合わせるのではなく、インターフェースがユーザーに合わせるようになったことを意味します。アンビエントAIがモバイル戦略の中心となる中、その勢いは、技術的な可能性だけでなく、自然で、高速で、手間のかからないエクスペリエンスを求める需要の高まりによって後押しされています。
Z世代がAIの未来を形作る
アンビエントAIの普及に漠然とした不安をお持ちの方、あるいはご年配のご家族への影響をご心配の方もいるでしょう。ご安心ください。使い慣れたエクスペリエンスを好むユーザーのために、従来の操作性を維持した端末も選択肢として残るはずです。一方で、テクノロジーは成長市場を追う性質があり、現在その可能性を示しているのはZ世代というわけです。
現在、Z世代は世界人口の重要部分を占めており、高い購買力を持っています。Bank of America Instituteのレポートによると、Z世代の所得は2030年までに36兆ドルに達し、2040年までに74兆ドルへと急増すると予想されています。それ以前の世代とは異なり、Z世代はスマートフォンやソーシャルメディアを通じてほぼ即座に情報にアクセスできる中で育ってきたため、デジタルプラットフォームを巧みに使いこなせます。Z世代は、AIがデバイスをよりスマート、パーソナル、直感的にし、アンビエントインテリジェンスを「あると便利なもの」から「なくてはならないもの」に変えることを期待しています。
AIが新しいUIになっていく中、ユーザーがテクノロジーを意識せず、感覚として刻まれる流れるようなエクスペリエンスを提供できるブランドが成功を収めるでしょう。そのため、次世代メモリへの投資は、単に速度や性能のためだけではなく、インテリジェントデバイスの時代において先行するための戦略なのです。
スマートフォンにとって「AIが新しいUIとなる」とは何を意味するのか
AIが新しいインターフェースとなる
AIをインターフェースにするには、「考えたこと」と「目に映るもの」との間に隔たりを感じさせないことが必要です。それを実現するのは、速度パフォーマンスと電力効率です。
超高速:会話、視覚、シーン理解など、遅延の影響を受けやすいやり取りでは、ユーザーの近くでコンピューティングを実行することで効果が高まります。オンデバイスAIにより、データセンターやクラウドとの往復遅延がなくなり、単なるリクエスト処理的な往復ではなく、真の「リアルタイム」なやり取りが可能になります。
- 電力効率:AI機能に求められるのは起動の速さだけではありません。バッテリーをすぐに消耗させたり、システムの速度を低下させたりすることなく、安定して動作し続ける必要があります。電力効率が重要である理由は、アシスタント、翻訳、カメラのAIには、低電力モードやスリープモードでも長いセッションを通じて応答性を維持しつつ、データを収集し続けることが求められるためです。
メモリはインタラクションの原動力
モデルの応答速度、会話のスムーズな継続性、バッテリー駆動時間など、AI使用時のあらゆるインタラクションやエクスペリエンスは、その一部をメモリ帯域幅と電力効率に依存しています。マイクロンは、帯域幅の拡大と消費電力の低減を実現する業界最高水準のメモリソリューションを提供するため、イノベーションを進めながら、主要なモバイルスマートフォンメーカーやチップセットベンダーと緊密に連携しています。
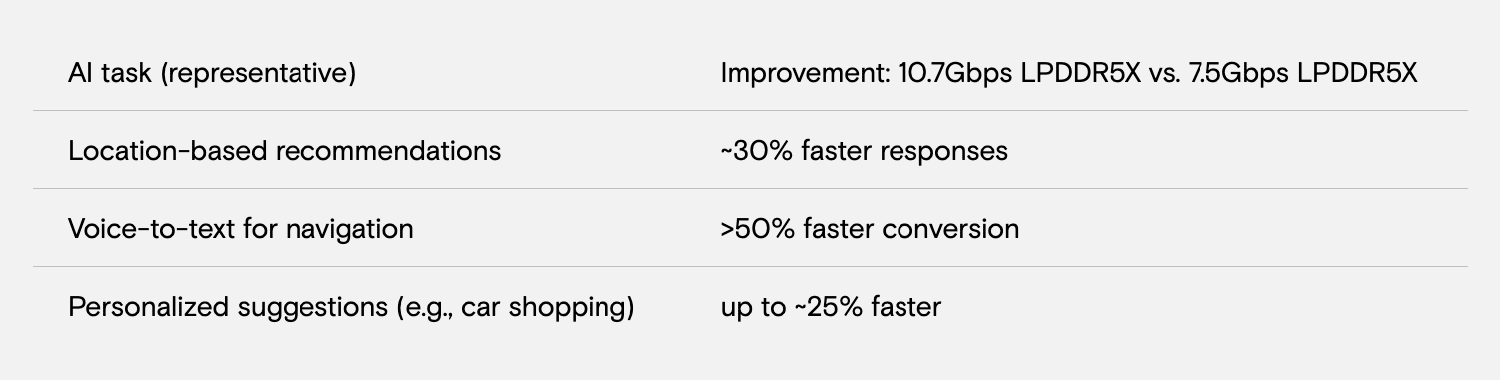
注:パフォーマンスデータはマイクロン社内の生産前テストに基づいています。結果はSoCや熱条件によって異なる場合があります。
- 帯域幅:マイクロンの最新メモリ「LPDDR5X」は、10.7Gbpsの最高速度を誇っており、最新のオンデバイスAIモデルにおけるリアルタイムのトークン生成や画像理解に必要な帯域幅を提供します。Llama 2を用いたパフォーマンス評価により、10.7Gbps 1γ(1ガンマ)LPDDR5Xを前世代の7.5Gbps 1β(1ベータ)と比較したところ、次のような結果が得られました。
- 電力効率:マイクロンのシステムレベルテストでは、高帯域幅と日常使用のシナリオにおいて、1γ LPDDR5Xは1βと比較して最大20%の省電力化が確認されました。この電力効率により、応答性の高いUIを維持しつつ、バッテリー駆動時間を伸ばせるため、ユーザーは1回の充電でAIアプリ、ゲーム、動画視聴をより長時間楽しむことができます。LPDDR5XのVDD2Hレールの低電圧版「LVDD2H」を用いた電圧スケーリングに関するマイクロンの最新の成果についてご確認ください。これにより、バッテリー駆動時間の延長、熱性能の向上、応答性の高いオンデバイスインテリジェンスの実現が可能になります。
具体的には、メモリ帯域幅が広がると、プロンプトを入力してからモデルが出力や最初のトークンを生成するまでの待ち時間が短くなります。また、電力効率が向上すると、たとえば通勤中ずっとリアルタイムで翻訳を実行するといったことも可能になります。
次世代メモリへの投資が競争上の差別化に重要な理由
オンデバイスAIの時代において、メモリは単なる技術仕様を超えて、戦略上の要となります。オンデバイスAIは、即時の応答、シームレスなマルチタスク、存在をほとんど感じさせない機能など、ユーザーがスマートフォンに期待する要素を変えつつあります。このような期待に応えるには、プロセッサーの高速化だけでなく、データがシステムの中をどれだけ早く効率的に移動できるかにかかっています。LPDDR5Xのような高度なメモリは、対話型AI、リアルタイムビジョン、バックグラウンドインテリジェンスをモバイルデバイスで実行する帯域幅と電力効率を提供します。
将来の展望
ユーザーはモデルのサイズを気にしません。記憶に残るのは、デバイス上でより早く、より長時間、プライバシーを守りながら、すべてが思いどおりに動作したというエクスペリエンスです。AIモデルの能力が向上し、エクスペリエンスがより豊かになるにつれ、メモリに対する要求は高まる一方です。そのため、マイクロンは将来のメモリテクノロジーに関して電子デバイス技術合同協議会と連携し、LPCAMMやSOCAMMといった新しいフォームファクタを実現しながら、帯域幅と効率をさらに高める機能を開発しています。
さらに、アンビエントAIエクスペリエンスがエッジデバイス全般に拡大するにつれ、LPDDR5Xは、その独自の高性能と最適な電力効率の組み合わせにより、次世代スマートフォン、インテリジェント自動車、AI PC、さらにはデータセンターの導入において有力な選択肢となります。マイクロンは現在、その基盤を構築しています。そのため、将来のデバイスはユーザーの期待に応えるだけでなく、それを再定義するものとなるでしょう。マイクロンのオンデバイスAIストーリーをもっと見る:データはエッジにとどまらない。マイクロンとともに加速する。


